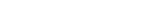2008年にスタートし、今年で15周年を迎えたART IN THE OFFICE。現代アートの新進気鋭アーティストを対象とした公募プログラムですが、その一環として、マネックス社員とアーティストの方が交流する機会も設けられています。普段あまり関わる機会のない方々との交流は、それぞれにどのような影響をもたらしているのでしょうか。今回は、2015年に受賞された蓮沼昌宏さん、2017年に受賞された橋本晶子さん、そして第1回から審査員を務めている塩見有子さんにお話をうかがいました。
アートとビジネスが混じり合うART IN THE OFFICEの特徴
―― ART IN THE OFFICEは15周年を迎えました。まずはこのプログラムがスタートした経緯をうかがえますか?
塩見さん:マネックスの代表である松本さんが前のオフィスにプレスルームをつくり、その壁に会社のロゴを置いたものの設置が難しく、置けなくなってしまったそうです。松本さんはもともと芸術文化に関心を寄せている方だったので、「この壁を現代アーティストのために提供しよう」と考えられ、私にお声がけいただきました。「こういうことを考えているが、どう思う?」と。あまり聞いたことがないアイデアだったので面白そうと思いましたし、なによりアートの側から見ても企画として十分成立すると思いました。そこから「じゃあ、やってみよう」となりました。

塩見有子さん NPO法人アーツイニシアティヴトウキョウ理事長
ART IN THE OFFICEでは第1回から審査員を務める
―― ART IN THE OFFICEはビシネスとアートの世界のあいだに立つようなプログラムに見えます。なぜでしょうか。
塩見さん:審査員として、松本さんを含めた2名のビジネスパーソンが参加されていること、それから社員の方を交えたワークショップを行なっていることが理由として挙げられるかもしれません。前者は松本さんのアイデアなのですが、アートの世界に身を置いた審査員ばかりでは、「あ、この作家さん知っている」というように時として視点が固まってしまうケースもあります。そのアーティストの過去の活動ももちろん重要ですが、ときにそこにひきずられて審査をしてしまう。
一方、松本さんともう1名のビジネス系審査員の方は、応募してきたアーティストのことを知らないことがほとんどです。だからこそ、提案内容そのものをビジネス的な視点を交えてジャッジしてくださる。それはほかのプログラムなどにはない、アートとビジネスが混じり合う独特なところかもしれません。
社員とアーティスト、立場の異なる人との交流がもたらすもの
―― ART IN THE OFFICEの特徴に、社員向けワークショップや、作品の制作をオフィスで行なう点が挙げられると思います。これにはどういった意図があるのでしょうか。
塩見さん:アーティストがつくった作品を、ただオフィスに置くだけでは、かなり一方通行なプログラムになってしまうと危惧したんです。ワークショップやオフィスで制作しているアーティストとの交流を通して「作家の存在がすぐそこにあり、社員が実体験として感じとることができる」というのは、何よりも変えがたい財産だと思っています。
.jpg)
2022年度のワークショップの様子
塩見さん:一方でアーティストにとっても、「普段、制作している場所を離れる」ことから生まれるものはあるのかな、と感じます。
蓮沼さん:そうですね。オフィスに通って制作しているとき、ぼくも社員みたいだな、と思いました。エレベーターを待っていると(代表の)松本さんがいて、「調子はどうですか」と声をかけてもらえました。1週間くらい通ったんですけど、自分のなかで良いと思える作品ができたんです。いつもとは違う環境でも出てくる絵はあって、自分でもそれを受け入れられたので良かったなと思いました。

蓮沼昌宏さん 「ART IN THE OFFICE 2015」受賞者
―― ART IN THE OFFICEについて、橋本さんはどのような印象を抱いていますか?
橋本さん:私はむしろマネックスの方々に「どのように見えていたか」が気になりました。マネックスさんには、聞いたところだと「アート部」というのがあり、ときどき一緒に美術館に行く方もいるようなのですが、そうした方々とお話をすると「こういう作家が好きなんだけど、どう思う?」といった話になるんですね。やはり、どこにでもアートに関心を持つ方はいらっしゃるんだなと。普段生活している世界は違うけれど、でもなんてことのない時間を共有できたことが印象に残っています。

橋本晶子さん 「ART IN THE OFFICE 2017」受賞者
蓮沼さん:ぼくも制作中にふらっと立ち寄って下さった方と少し話をしたんですけど、その人がぼくの作品の主題の一つとしている「物語」について反応をしてくれて。「自分は株の分析とかリサーチをするけど、最終的には物語が必要なんじゃないかと思ったりする」とおっしゃっていました。そうやって急に来て、深い話をぽろってしていかれる方がいたことは面白かったですね。

2020年には富山美術館でワークショップ、ギャラリー展示「物語の、準備に、備える。」を行なった(撮影 柳原良平)
―― 第1回から審査にも携わっている塩見さんから見て、お二人の作品はどのような点が印象的でしたか?
塩見さん:蓮沼さんは「新しい昔話」という、タイトル自体が矛盾していて面白いなと思ったのですが、その物語を社員と一緒につくっていくというのが魅力的でした。どこかに不可解なところとか、これって「どういうことなんだろう」とか、その不確かさ、掴みにくさが重要だと思っていて。そういう部分が印象深かったですね。

受賞された蓮沼さんの作品
「新しい昔話」(2015年)
塩見さん:一方で、橋本さんの作品は空間の切り取り方が印象的でした。鉛筆で描く技術力ももちろんなのですが、視覚が捉えている以外の空間を想像させる、空間の広がり、意識の飛ばし方とでもいうものにとても惹きつけられました。

受賞された橋本さんの作品
「There is something I want to talk about.」(2016年)
―― どちらの作品も塩見さんとしては魅力的だったんですね。ただ、審査のときは、アートの視点からだけでなく、ビジネスの視点を持った方も一緒に話し合っていくと思います。異なる視点から作品を見て議論を重ねることは、大変ではありませんか?
塩見さん:たしかに審査の過程ではいろいろな議論を重ねますが、お互いに気づきがあって良いことだと思います。「どうしてその作家が良いと思うか」と意見を出し合い、聞き合う。否定するでも、肯定するでもなく、「ああ、こうやって見ているんだ」と。始まる前に「審査会をするのは不安だな」と思うことはあっても、それでも毎年「この人にしよう」と審査員の意見が重なっていく瞬間は必ずあるんです。なるだけ言葉を尽くす、ということは意識しているように思いますね。

「There is something I want to talk about.」の一部
当時の審査員である株式会社リブセンス代表取締役社長の村上さんからは、
「観る人がどう感じるかを熟考している様子が伝わってきました」とコメントがあった
―― 社員アンケートによると、ART IN THE OFFICEが「多様性の理解促進につながっている」と答えた方が6割に上ったそうです。それについて感じたことなど聞かせてください。
橋本さん:私としては社員さんとアーティストのあいだで線を引くのではなく、人間として一人ひとりの違いを感じながら交流をすることができたなという印象が強かったです。社員さんからはもしかしたら、アートという全然違う世界にいる人、と見えたかもしれません。けれど、何でもない会話やワークショップを通して見えてきたのは、何といいますか、個人にじわじわ入り込んでいく、というか。多様性という言葉で片づけるより、そうやって一人ひとりとのつながりを持てたことが何かになるのかなという感じがします。

橋本さんのワークショップの様子
蓮沼さん:少し安心するのが、アンケートで4割が「そう言い切れないよ」と言っている、というところかなと。ぼくはその4割の方々にも「そうだよね」と思えるというか。アートに関わることが多様性につながるかどうかも疑って良いなと思っているし、そういうことをわざわざ考えるのが自分の職業かなとも思っていて。そこの部分を含めて、疑問を持ったり、話をできたりするのは良いなと思っています。何か考えを押しつけるんじゃなく、文句の余地があるっていうのが、まさに開かれているという気がして。珍しい言動をする人を連れてきて、それが多様性なのかといわれると、ぼく個人はどうかなとは思ったりするのですが、その「どうかな?」を一緒に考えられる感じが嬉しいなと思うんですね。

蓮沼さんの作品『新しい昔話』では、「小笠原諸島に生まれつつある新しい島と、
気流にのってそこに辿りついた空想のアリ達」を切り口に物語が描かれている
今後のART IN THE OFFICEへ期待すること
――ART IN THE OFFICEは、企業や社会をアートとつなげる役割も持っているように感じます。塩見さんは、どのようにこのプログラムに取り組んでおられますか?
塩見さん:あくまで私自身について言うと、私は結構カメレオン的な立場をとることが多いんです。(笑)企業には企業のルールがあり、ニーズがあり、あるいは「ここからはできない」というのもある。そこは必ず留意して配慮していきますけど、一方でそれはアーティストも同じなんですよね。アーティスト側も、自分たちが大事にしていることがはっきりとある。「こういうふうにはできない」あるいは「こういうふうにやりたい」と。だから必ず両方を見て、時と場合によってアーティスト側に、企業側に立ちながら接点を探るような、そういう取り組み方をしてきたつもりです。それぞれ文脈が違う者同士でも、何かちょっとした考えを提示することで「ああ、そういうことだったんだ」と理解できるケースもありますから。お互いの接点を見つけて耳を傾けてもらう努力といいますか。
――両者の接点を探して、耳を傾けてもらう。重要な役割だと思います。
塩見さん:今日、あらためてお二人の話を聞いていて、やはり企業側とは異なるロジックを持っていると感じました。そうしたアーティスト側の視点を企業側にしっかり共有できたら良いなと思います。

塩見さん:「これをしたら何かにつながりますか?」と別のインタビューにあったと思うのですが、そうした問いに、企業的な視点をみることができると思いました。というのもお二人の頭のなかでは、「これをやったらすぐこうなる」と、「イン」と「アウト」のように直線的には考えていなくて、むしろあちこち迂回したり、立ち止まったり、時に停止したりしながら、時間をかけて思考を深めていく。アーティスト側と企業側でそれぞれ違った物事の進め方や考え方、捉え方がある。そこが面白いところでもあると思います。お互いに違うロジックを持っていて、どちらかにまとまる必要もありません。「それぞれみんな違うんだよ」というのを意識しながら日々を過ごすだけでも、世の中が違って見えてくるのかなと考えています。
―― アーティストから見て、今後のART IN THE OFFICEに期待すること、あるいは「ここを良さとして持ち続けてほしい」と思うことはありますか?
橋本さん:ART IN THE OFFICEでは1年間、制作した作品をこのオフィスに納めていただけて、さらに終わったあとも作品の一部分を社内に飾ってくださっているんですね。その「作品の一部分が残り続ける」というのが、やはり良いなと。

橋本さん:作家として活動を続けていると、つくったものがあちこちに産み落とされていく感覚があるんですけど、そういった「どこかに残っている」という感じがつくっている側としては腑に落ちるところがあって。過ぎ去っていくんじゃなく「その一つがここにある」というのが良いなと思っているので、そこは続いてくれたら嬉しいです。
――蓮沼さんはいかがですか?
蓮沼さん:そうですね……。もう少し訳のわからない枠組みのプログラムがあっても良いかな、と思ったりします。「これが作品?」と感じさせるような表現があってもいいのかな、と。
.jpg)
蓮沼さん:もう15年も歴史があるので、ART IN THE OFFICEにはそういう土壌ができてきていると思うんですね。「こういう作品を表現としてやっている人がいるんだ」と知ってもらう機会にもなる。そういうものまでART IN THE OFFICEが受容してくれると、もっと面白味が出るかなと思っています。
―― インタビューは以上です。ありがとうございました。

.png)